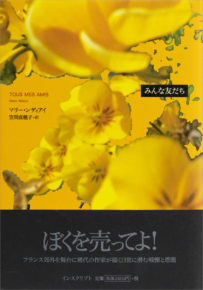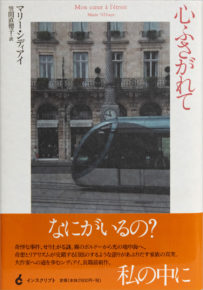去年の九月初旬、写真家のOさんと秩父市大滝をまわった。いつか泊まろうと思っていたTさん経営のゲストハウスに一泊し、翌日は両神山へ行こうかと話していたのだけれど、降ったり止んだりの不安定な天気なので諦め、御岳山を途中まで登ることにした。一時は霧につつまれた山歩きの帰り道、舗装された車道まで出て坂道を下っていると、なんとも言えず品のよい芳香が運ばれてきた。甘く、濃いのだが、野性味はなく、まるみと温かさのある匂い。出どころを探すうち、足元に赤紫色の花弁が散っているのにOさんが気づいた。一緒に真上を見あげると、垂直の擁壁をまんべんなく覆う幅広の葉のあいまに、地面に落ちているのと同じ赤紫の、藤の花を上向きにしたようなかたちの花房があり、下半分はすでに茶色く枯れている。写真に撮り、あとで調べたところ、クズだった。花の匂いは、ぶどうやワインの匂いと表現されることもあるようだ。
クズは、日本全土に分布するマメ科の多年草。根から取ったデンプンで葛餅や葛切りなどの和菓子をつくる、あのクズで、秋の七草にも入っている。また、漢方薬の葛根湯は、文字どおりクズの根を乾燥させたもの。非常に親しみぶかい草のはずなのに、植物としての形状を知らずにいた。葛粉とも、葛根湯ともずいぶん感じの違う、あでやかな色と香りの花だった。
けれども、今日、この植物の第一の特徴として挙げられるのは、花の美しさではない。
クズは、つるをどんどん伸ばして成長し、壁があればつたい、なければ地面を這って根を下ろしながら進出する。際限なく「はびこる」ので管理が難しいとされ、インターネットで検索すると、薬品を使った駆除の指南があれこれと掲載されている。また、日本から海外に持ち出されて野生化した結果、世界各地で他の植物を圧迫するほど繁茂しており、とりわけアメリカ合衆国では南部を中心に広がる「侵略植物」として悪名高い。環境保護団体のウェブサイトなどで、樹木も建築物もふくめ風景全体が、あたかもクリストの現代美術作品のごとく、すっぽりとクズの絨毯に覆われた写真を見ることができる。
日本では、セイタカアワダチソウ、セイヨウタンポポ、より最近ではナガミヒナゲシといった「外来種」が、日本の在来植物を脅かすとして、駆除の対象となってきた。環境保護の名目で、こうした植物を「除草」する活動には、わたしの友人も、無論、善意から、参加したことがある。さらには、野草のうち外来種だけに印をつけて引き抜いていくワークショップなどもおこなわれているようで、指導する造園家が、外来種の野原は色が濃い、在来種のほうが淡い優しい色をしているといったことを述べるのも目にしたが、そのように外来種・在来種を対立させ、後者について一律に肯定的な評価をあたえるのは、発言者の意図はどうあれ、排外主義にまっすぐつながっていく。
「外人」は(と、こうしてあらためて字面を眺めるにつけ、なんとひどい言葉だろうと思うが)、おしなべて雑で、主張が強く、無遠慮であり、対して繊細で控えめで思いやりのある「日本人」はつけこまれやすい、という、それ自体すでに差別的で高慢な自己認識は、日本という国の攻撃性を裏から支えてきたもので、今日なお衰える気配を見せないが、まったく同じ物言いが、動植物の外来種をめぐる固定観念に、あからさまに反映されている。
古来より国内で愛され利用されてきた植物であると同時に、色が濃く、繁殖力が強く、鮮やかな色と香りの花を咲かせ、日本から海外に持ち出されて「猛威をふるう」クズ、という存在は、この国に蔓延する排除の言説の前に立ち止まるきっかけとはならないだろうか。
ジル・クレマンの『動いている庭』には、まさに「侵略的」とされる植物の一例として、クズが登場する。ただし、こうした植物が「生態系を破壊する」という言説に、クレマンはくみしない。「実のところ侵略とは、ある生態系のなかで、そのときまで空いていた場所を占拠することでしかない」(クレマン『動いている庭』山内朋樹訳、みすず書房、2015年、20ページ)し、群落が形成されるのは多くの場合、過渡的な段階であって、その後、群落の衰退とともに、土地は安定した極相状態に向かっていく。クズがはびこったが最後、ずっとそのまま、ということは考えにくいのだ。実際、完全に一種類の植物のみが広範囲に育ちつづける環境が存在しうるとすれば、それは人間のつくった農地以外にはありえないだろう。
クレマンは、「侵略的」な植物については、その働きを受け容れつつ、ある程度の管理や方向づけを行うこともできるはずだと述べた上で、こうつけ加える——「侵略的外来種を撲滅しようとすることは、この侵略の働きの前に屈したことを認めることに他ならない。というのも、それはわたしたちの現在の知識が暴力にたよる以外の手段を知らないことを示しているからだ」(同書、20ページ)。
また、彼は、多様な植物が年ごとに自由に庭のなかを移動していく「動いている庭」をつくるにあたり、多品種の野草の種を混合したものを撒くことを提案するが、それらの種のなかには外来種がふくまれている。この点を非難するであろう人々に向けて、彼はおおむね次のように説明している。
用意される種のブレンドは、さまざまな環境条件に適した植物を組み合わせてある。撒いた種の要求する条件が、撒かれた土地と合わなければ、その種は芽を出さない。温度、湿度、日照、その他無数のふるいにかけられて、それでも発芽したならば、原産地がどこであろうと、その植物はその土地の現実の一部となる。外来種か在来種かで選抜するのは、「自然を尊重すると言いながら、突如としてイデオロギーに従わせることだ」(同書、135ページ)。
こうした書き方から、外来種の敵視が人間世界の排外主義に直結するものであると、クレマンが明瞭に意識していることが見てとれる。荒れ地に自生する植物相が、遠い土地からやってきた外来種と、元々その土地を代表する在来種との混淆から成り、それこそが「明日の風景」(同書、70ページ)を見せるものだとする彼は、そもそも本書の冒頭から「生はノスタルジーを寄せつけない」(同書、16ページ)と断言している。彼の修景論に、起源の幻影に寄りかかった純血主義の入りこむ余地はない。
さて、大滝で撮ったクズの花の写真は、地面に落ちた花弁と、枯れかけた花房だけで、きれいな状態の花は撮影できていない。クズの話を書くなら、もう少しよい写真がほしいけれど、撮影しに行こうにも、いまの季節に咲いているわけもない……と考えていたら、火花が散るように、不意に記憶がよみがえった。
大滝行きのちょうど一年前、つまり一昨年の九月初旬、わたしは済州島にいた。海辺の巨大な岩山、城山日出峰(ソンサンイルチュルボン)をのぼる途中、海風に乗って馥郁たる香りが漂ってきた。わたしは匂いの元を突き止めようと、展望台の欄干から身を乗り出し、崖を埋めつくす緑のなかに赤紫の花が咲いているのを見つけ、写真に収めた。
そのときの写真を探した。間違いなく、クズだった。すでに出会っていたのだ、海の向こうで。