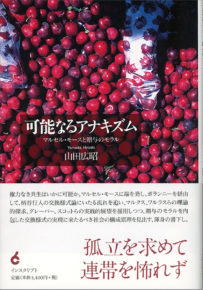千里丘陵といえばその景観の中心が、平地部の水田を囲むようにして拡がる竹林と桃畑からなるという時代があった。竹林はその面積を大きく減らしたとはいえ今もまだ健在だが、桃畑についてはもはやほとんど見ることができない。だが、千里山住宅地の開発が始まった1920年ごろには、千里山はどうやらかなり知られた桃の名所であったらしい。それも口に入れる果実としてだけでなく、春の花見の名所としてもである。花見といえば、ふつうは桜か梅を思うところだろうが、当時は桃の花もまた春の行楽の対象でありえたようだ。吹田の郷土史家である池田半兵衛氏の編纂になる写真集『吹田』には、「河田山(こうだやま) 〔千里山住宅地が造成されたあたりの高台の旧称〕は「桜は吉野、桃は河田」というぐらいで、大阪・神戸からも花見客が絶えず、頂上に紅白の幕を張った茶店があり、唄声と三味線の音で終日賑わった1*1『ふるさとの想い出 写真集 明治・大正・昭和 吹田』池田半兵衛編、国書刊行会、1985年、p.44.」との記述がみられる。
桃が千里でいつごろから栽培され始めたか、某不動産会社がネット上で公開している「このまちアーカイブス」の千里篇によれば2*2https://smtrc.jp/town-archives/city/senri/index.html (三井住友トラスト不動産)、(残念ながら典拠は示されていないのだが)「桃は江戸末期から、現在の上新田・下新田のあたりで栽培が始まった」とされていて、花見が終わって夏になれば、「たわわに実った桃の実は、大阪の「天満市場」に出荷されたほか、缶詰にも加工され、売り出されていった」とある。ただ、それには続きがあって「しかし、大正初期に害虫が大発生して、多くの地区で桃が全滅し、筍作りへの転換を余儀なくされた」と書かれている。ただこれは私自身の記憶とはうまく折り合ってくれない。というのも、幼少期(1960年代)の私の記憶に間違いがなければ、下新田から上新田にかけての山の斜面は、当時なお、桃畑が全盛だったからである。桃栽培にかんして欠かすことのできない作業のひとつに、桃の「袋着せ」というかなり手間ひまのかかる作業があるが、小さい頃私はその作業に桃畑に出かける親によくついて行ったものだった。もっとも目的は虫取り(昆虫採集)で、例のごとく、親の手伝いをすることではなかったけれど。
戦前から戦中期をまたいで少なくとも60年代半ばまで、このあたりの地区では桃栽培がさかんであったことは、その後に開発された千里ニュータウンの地区名のひとつとして、下新田村の近傍では「桃山台」が選ばれていることからも分かる。つまり、大正初めの虫害による桃の木の全滅によって、主要作物が筍栽培へと一気に切り替わったというより(地区によってはそうしたこともあったのかもしれないが)、桃と筍は長きにわたって千里丘陵の二大特産品として並存を続けていたのである3*3『下新田村郷土史』(春日町青年学級編、1962年)は,、昭和に入ってからの出来事として水田から果樹畑への転換について触れている。桃の作付けの変遷に関しては、次のように書かれている。「果樹のうち最も重要な桃は、明治七年九千五百貫、八年七千二百貫、九年五千貫が、大正三年でも六千貫と変化ない。それが昭和四年には二万八千貫となり、この期間になっていちじるしく発展したことを知ることができる。」(p.63.)。ただし、桃畑が竹林へと変わっていったというのは、わが家のケースにもある程度当てはまる。桃は果樹としての寿命が比較的短く、老木や枯木を更新せずそのまま放置すると、隣接する竹林から竹が侵入してきてあっというまに竹林に変わることになる。現在残るわが家の竹林の一部はそうした侵入によってできたものだ。とはいえ、ただ侵入するにまかせておけば筍の獲れる竹林になるのではなく、毎年ちゃんと間伐を行って適切な本数に管理をすることは必須の仕事であり、この仕事を怠ったりすれば筍畑になるどころか、数年で足も踏み入れられないほどに密集したただの「竹藪」になりさがってしまう。
桃について、もう一言しておけば、十数年前に苗木から何本か定植し直してみてよく分かったのだが、この果樹はじつに気難しい。病気や虫害にとにかく弱いのである。手を入れるのは剪定だけにして、農薬散布はいっさいしないで作ってみようとしたら、まったくといっていいほど実が成らなくなったうえに、半数以上が枯れてしまった。似たような世話の仕方をしていても、柿の方は毎年それなりに実をつけ続けているというのにである。(こちらも実が色づくと烏に持っていかれるが、それはまた別の問題である。)
桃と並ぶ千里丘陵の特産品たる筍についていえば、これはわが家にとっても、村全体にとっても別格に重要な作物だったと言い切れる。筍が出てくるのは、3月の20日頃から4月末までの一月半ほどだが、その期間、村の農家で竹林を所有している家は、筍掘りとその出荷作業にほぼ全集中状態になる。朝市に間に合うように日の出前から掘り始め、家に帰って出荷作業を済ませると、今度は昼の出荷(ツケ市と呼ばれていた。遠方の缶詰業者がトラックで仕入れに来る)に向けてまた竹林にもどって掘る。筍は地面に顔を出すかださないかのうちに掘るのがポイントなので、使う道具も特殊な形状をしており(私たちはたんにホリと呼んでいるが)、土中の筍の方向をすばやく判断して傷つけず、しかも短時間で掘り出すには、それなり以上の熟練がいる。ところが苦労して掘りあげた筍に、労働になんとか見合うと思える値がつくのは、初市からせいぜい10日間ほどで、4月に入って最盛期を迎えて出荷量が増えたとたんに卸値は悲しいぐらいに下落する。それが悔しいというのと、冬場に乏しくなる現金収入を確保するという目的があって、うちでは家内工業的に水煮の缶詰を作っていた。裏庭の地面を掘り下げて作った二つの竈に大釜を乗せ、柴小屋一杯に積んでおいた間伐竹や剪定枝を燃料に、大量の筍を皮ごと釜に投げ込んで茹で上げる。茹でたあとの湯は筍から出たアクで真っ黒になる。茹であがったら地面に放りだし、手で触れる程度に冷えるのを待って皮を剥き、冷水を張った大樽に次々と放り込んでは、三日ほど流水にさらす。それからようやく缶(一斗缶)に詰めて再び大釜で煮沸し、なかの空気を追い出すために開けておいた穴をハンダで詰める。こうして作った缶詰を秋になってから、たぶんおせちの需要を見込んで、売るのである。これが年中行事だったために、私は実家を出たあとも4月になると大量の筍を大釜で茹であげたときの匂いをよく思い出した。
この缶詰作りをいつからやらなくなったのかをちゃんと記憶していないのだが、少なくとも二十数年前に父が亡くなるまえにはもうやめていたと思う。その後、裏庭の竈も埋めてしまって現在はない。ただし、筍の大阪の青果市場への出荷だけは今も続けている。旧下新田村にはほかにもまだ十数軒、筍の出荷を行っている家があり、ご多分に漏れず高齢化と後継者の不足によって風前の灯火だとはいえ、筍の出荷組合は健在である。

さて、この農園通信では、第4回で、1920年代における山田村での小作争議について書いた(「小作争議と養鶏」)。そして、その締めくくりに、私は山田村の小作争議のみならず当時全国的な高まりを見せていた農民運動全体が大きな変質を強いられる原因のひとつになった出来事として、1930年代初めの昭和農村恐慌があったことに言及した。繰り返しにはなるが、連載の間がずいぶん空いてしまっているので、該当箇所をここに引いておきたい。
1930年から数年の間、日本の農村は昭和農業恐慌と呼ばれる深刻な恐慌におそわれる。これを受けて政府側が打ち出したのが「農山漁村経済更生運動」である。1932年(昭和7年)から毎年1000町村が、1940年(昭和20年)までには全国の81%にあたる9153町が、経済更生指定町村に指定された(われらが下新田村もこの運動がはじまる初年度に経済更生村としての指定を受けている)。この運動はきわめて精神主義的色合いが強いもので、指定を受けた農村に補助金と引き換えに、「挙村一致による自力更生」を求めた。山田村の農民運動の敗北が決定的なものになるのは、この経済更生運動に組み込まれていくことによると言ってもいいだろう。1933年(昭和8年)12月、全国農民組合山田村支部は支部決議にもとづいて全農大阪府聯合会に脱退届を提出する。代わりに彼らが参加するのは、まさにその12月に結成される「皇国農民同盟」である。農民組合の右旋回のはじまりである。
昭和農業恐慌のきっかけとして挙げられるのは、1929年のアメリカにおける株価暴落にはじまる世界恐慌の一環として、生糸の対米輸出が激減したことによる生糸価格の暴落である。引きずられるようにして他の農業生産物の価格も下落するが、なかでも影響が大きかったのは、日本農業の基幹をなす米価の下落である(下落が始まった1930年は皮肉なことに豊年であったらしい)。北摂の農村地帯では養蚕は行われていなかったから、私には実感が湧きにくいのだが、当時の日本の農村経済は米作と養蚕を二本の柱として成り立っていた。山梨県石和生まれの深沢七郎の(彼自身は農家の出ではないが)『甲州子守歌』には、繭につけられた値段のあまりの低さに憤慨して売らずに市場から持ち帰り、途中で橋の上から川にまるごと投げ捨ててしまう男の話が出て来る(ただし物語上の時代は昭和恐慌からは、ずれている)。
「あんたのうちのヒトでごいすけ、川へマユを流したのは」
と母親(おかあ)が言った。
「そうでごいす、マユの値が安すぎたから、うちのお父うさんが怒りだして、うちのお父うさんは短気だから、”そんねん安いんじゃア、捨(ぶちゃ)った方がいい”と言って、売らなんで川へ流してしまって」
と言うのである。
農山漁村経済更生運動に関して、『吹田市史』第七巻(資料編)には「三島郡新田村経済更生計画」(昭和8年(1933年))、「経済更生村三島郡新田村行脚記録」(昭和10年(1935年))、「三島郡山田村経済更生計画」(昭和10年)という三つの資料(作成者はすべて当時の大阪府経済部)が収められている。目を通してみるとこれがなかなかに面白い。もちろん典型的なお役所文書なのだが、それゆえにこの官製運動の指導理念(イデオロギー的基盤)がどんなものだったかがはっきり読み取れる。「新田村経済更生計画」を例にとれば、計画は「精神作興計画」(これがトップにきている点がいかにもである)、「生産増殖計画」「経済行為是正」「社会及生活改善計画」という四つの要項に区分され、それぞれに現況、更生要点、施設要項、実行年度、主たる実行機関を示すという構成を取る。「生産増殖計画」をのぞいて、残りの三つの要項には下位項目がさらにあって、「精神作興計画」では第一は「聖旨の徹底」であり、「敬神崇拝」、「団体の認識強化・国家観念の強化」と続く。あわせて村史の編纂と図書館の設置という項目が立てられているのは、隣村の山田村の更生計画には見られない特徴だが、これは実行年次が五カ年計画の第五年次になっていていかにもお題目といった感が強い。
「経済行為是正」には、「産業組合の設立」「筍の加工」「農産加工」の三つの細目が、「社会及生活改善計画」には「地主小作間の協調」「社会及生活改善」という二つの細目が立てられている。話の流れから他にまして目を惹くのは、前者では「筍の加工」であり、後者では「地主小作間の協調」であるが、計画書からそれぞれ現況報告を引いておくと、前者は「筍缶詰は従業戸数八戸、加工数量三九・九〇五貫価額一三九六七円の生産あり。筍の生産は三十四万貫」、後者は「地主小作間の関係は府下に於ても相当知られたる紛争の地にして其の面倒を免れる方法として下新田は果樹栽培を自営し来れるも上新田に於ては地主階級多く多少緩和の徴あるも年々減免問題あり」とある。
果樹栽培が小作争議の緩和剤になるというのは、不思議にも思えるが、小作料は米による現物納入が基本であったことを考えると、ある程度納得はいく。下新田村で激しい小作争議があったということを聞かない理由の一つとして、この村では果樹栽培にくわえて、筍がその主要産物であったということが関係しているかもしれない。「更生計画」から二年後の「新田村行脚記録」では、下新田村の缶詰工場を視察した話が出てきて、そこでも村の主要産物が筍であることが強調されている。行脚記録に曰く、「新田村は三百年位前から次第に開かれた土地で全村の大部分は丘陵地から成り、それが開かれて筍藪や果樹園となっている。[…] 筍の生産額は三十五万貫、此の価額四万四千円に上り、村の主要産物で、見渡す山々これ竹林ならざるはなく頗る壮観である。[…] 筍の栽培はさすがに主要産業だけあってよく発達し、管理の行届いていることは感嘆の外はない。」ちなみに下新田村に筍の缶詰工場があったことを私は村史を調べ始めるまでは知らなかった。缶詰工場は私が物心がつく頃にはもう存在していなかったのである。かわりにカシミア工場が川沿いにあったのだが、そこが缶詰工場の跡地ではなかったかと勝手に推測している。村内にはほかにそれらしい場所が見当たらないからである。

このまま終えたのでは話があまりにもローカルなので、すこし話題を一般性のある方向に開いておきたい。
新田村行脚記録には上の報告に続けて、缶詰工場が組合方式で経営されていたことが書かれている。少し長くなるがそのまま引用しよう。
此の本村の主産物たる筍の販路に付ては、例年其の最盛期に於て仲買人の結託により価格を左右せられ多数生産者は随分ひどい目に遭ふことも少くはなかったのである。ここに於てどうしても生産者自ら筍の加工に依り価格の調節を計らねばならぬということが識者の間に予て考へられていたが、然し何分多額の固定資金を要することであるから、容易に実現せられなかったのであるが、上新田に於ては昭和四年農事実行組合の設立と共に其の議熟し、府の奨励に依り組合員中意志の強固なるもの三十五名を以て昭和五年三月初めて筍缶詰組合を設立し、下新田に於ては之に習と昭和七年二月同じく組合を設立した。共に当初は幾多の困難と闘ふが組合役員の熱心は遂に着々成功し、今日に於ては此両組合の加工場の為に価格大に調節せらるるのみならず、此の加工に従事する村の男女に労賃を与へ、其の有形無形の利益頗る大で村民は安心して此の広面積の筍の栽培に従事することが出来る様になっている。
つまり農山漁村経済更生運動は、村民たちに各種の組合を結成することを奨励していたのである。昭和農業恐慌下の農村を全国行脚して、農民たちを中心にして聞き取りをおこない、その調査結果を『踏査報告 窮乏の農村』(1934年)としてまとめた学者に、農業政策と経済学史を専門とし、確信的なマルクス主義者であった猪俣都南雄がいる4*4猪俣津南雄『踏査報告 窮乏の農村』岩波文庫、1982年。。同書はイデオロギー色をできるかぎり抑えて(検閲を意識していたためもあろうが)事実に即して語ろうとしている点で、当時のことを知る貴重な資料となっている。同書は初篇「窮乏のさまざまな型」、中篇「農民から観た農村対策」、終篇「農民の喘ぎ求めるもの」の三篇からなるが、その中篇で猪俣は「経済更生運動」の実態の分析に多くの頁を割いている。猪俣が運動に向けている視線はじつに辛辣である。「今やっている農村経済更生五カ年計画なるものは、実践されない計画であるばかりでなく、計画のない計画である。」(p.127)しかし彼によれば、計画がただのお題目、計画のための計画であることは、農民にとってむしろ幸いなのだ。「計画通りにやるものもないしやれるものが余りないからまだいいようなものの、もし本当にどこでも実行することにでもなろうものなら、五カ年計画は恐らく三カ年で成果を収め、更生による過剰生産恐慌が全農村を襲うことだろう。」(p.128)
そして、猪俣の筆は「更生計画」がさかんに奨励している産業組合(生産組合、出荷組合、購買組合、信用組合)に及ぶ(中篇3.「産業組合と貧農大衆」)。彼の評価はこうである。「資本主義の環境の中におかれた産業組合なるものは、元来が至って弱いものである。それに産業組合の主なる活動の領野は、生産の部面にはなく、流通の部面にある」(p.129)「—これはよく知られていることだが—出荷組合それ自体は大きな商業資本や工業資本に隷従した組織にすぎない場合が多い。出荷組合は小さな「中間商人」を排除するが、それは農民のために排除するのか、大資本のために排除するのかわからない。」「何といっても流通部面での仕事だから出荷組合がやることはたかが知れている。第一に出荷するほどの生産物がなければなんにもならぬ。第二に、価格に対する支配力がなければなんにもならぬ。第三には、多数農民の懐具合が、すぐに現金をくれない出荷組合を利用するだけの余裕がないようでは何にもならぬ。」(p.133)
猪俣のこうした評価は、流通部門に対して生産部門(生産諸関係)を重視する正統マルクス主義者の立場を反映しているとも読めるが、述べられていること自体は納得がいく。しかし、産業組合の結成を強く奨励した側である政府の狙いはいったいどこにあったのだろうか。岩波文庫版『窮乏の農村』の解説(大島清)は、農村経済更生運動の目的を次のようにまとめている。「この運動は、政府が農村末端にいたる行政機構と産業組合の組織を通じて地主と農民を官僚的に統制しつつ、彼らを体制内に再編成しようと計った政策である。これは地主・小作の階級闘争を排し、地主と自作農を中心に農村平和を維持しつつ経済の崩壊を防ごうという狙いがあった。単なる一時的恐慌対策というよりは、昭和恐慌を契機に明確な形をとりはじめた国家独占資本主義的な農村掌握政策とみることができる。」(p.235)
事後的にみれば、たしかにそう言えるのだろうが、私が興味を惹かれるのは、体制内に取り込む目的で各種の産業組合を奨励した背景に、フランスの政治家レオン・ブルジョワの思想に代表される「社会連帯主義」(マルセル・モースも広い意味ではこの流れに属する)の(日本化された)受容があるのではないかということである。内務省社会局の田子一民や、同じく社会局の嘱託をつとめ、社会事業の展開に大きな影響力があった生江孝之らは、早くから社会連帯主義に関心を寄せていて、彼らの事業の理論的基盤に据えようとしていた5*5池本美和子「日本における社会連帯論—道徳的規範を超えられるか—」「社会学部論集」第37号、佛教大学社会学部、2003年9月。丸山岩吉『社會連帶主義』(早稲田泰文堂、1923年)、『レオン・ブルジョワ氏論文集 ソリダリテその他』(桃井京次訳、 國際聯盟協會出版、1926年)といったあたりが社会連帯主義の日本に於ける最初のまとまった紹介ではないかと思えるが、1930年代に入るとシャルル・ジッド、レオン・ブルジョワ『社会連帯責任主義』(松浦要訳 、日本評論社、1932年)、レオン・ブルジョワ『社会連帯責任主義とは何か』(堀田健男訳, 中央報徳会、1933年)6*6本書は翻訳と言うより、レオン・ブルジョワの思想内容を要約解説したものであるが、著者の堀田健男もまた内務官僚である。なお、社会連帯主義についてのこうした邦語文献について知ったのは、宮代康丈氏(慶應義塾大学)のご教示による。など立て続けに翻訳や紹介書が出版されている。とくにこのときソリダリテが「社会連帯主義」ではなく、「社会連帯責任主義」と訳し直されたことは、社会連帯主義の日本における受容のされ方を考えると、象徴的なことに思える。「連帯責任」という言葉は、戦後も学校教育の現場ではよく口にされ、いやな記憶しかもたない人間は私だけではないのではないだろうか。この問題の詳細については、社会連帯主義の本来の趣旨が如何なるものだったかも含めて、次回以降に譲りたい。
[1] 『ふるさとの想い出 写真集 明治・大正・昭和 吹田』池田半兵衛編、国書刊行会、1985年、p.44.
[2] https://smtrc.jp/town-archives/city/senri/index.html (三井住友トラスト不動産)
[3] 『下新田村郷土史』(春日町青年学級編、1962年)は、昭和に入ってからの出来事として水田から果樹畑への転換について触れている。桃の作付けの変遷に関しては、次のように書かれている。「果樹のうち最も重要な桃は、明治七年九千五百貫、八年七千二百貫、九年五千貫が、大正三年でも六千貫と変化ない。それが昭和四年には二万八千貫となり、この期間になっていちじるしく発展したことを知ることができる。」(p.63.)
[4] 猪俣津南雄『踏査報告 窮乏の農村』岩波文庫、1982年。
[5] 池本美和子「日本における社会連帯論—道徳的規範を超えられるか—」「社会学部論集」第37号、佛教大学社会学部、2003年9月。
[6] 本書は翻訳と言うより、レオン・ブルジョワの思想内容を要約解説したものであるが、著者の堀田健男もまた内務官僚である。なお、社会連帯主義についてのこうした邦語文献について知ったのは、宮代康丈氏(慶應義塾大学)のご教示による。
山田広昭(Hiroaki Yamada)
フランス文学、思想。東京大学名誉教授。大阪府生れ。著書に、『現代言語論』(共著、1990年)、『三点確保─ロマン主義とナショナリズム』(2001年。以上、新曜社)『可能なるアナキズム─マルセル・モースと贈与のモラル』(インスクリプト、2020年)など。
最近の論考に、「全般経済学と純粋アナーキー原理」(『はじまりのバタイユ』所収、法政大学出版局、2023年4月)、「希望の原理としての反復強迫」(『群像』2023年2月号)、「不順国神(まつろわぬくにつかみ)、あるいはセイタカアワダチソウと葛の間を歩む者──「絶対小説家」大江健三郎を悼む」(『ユリイカ』2023年7月臨増 総特集=大江健三郎)などがある。
訳書に、『ヴァレリー集成IV:精神の〈哲学〉』(編訳、筑摩書房、2011年)他。