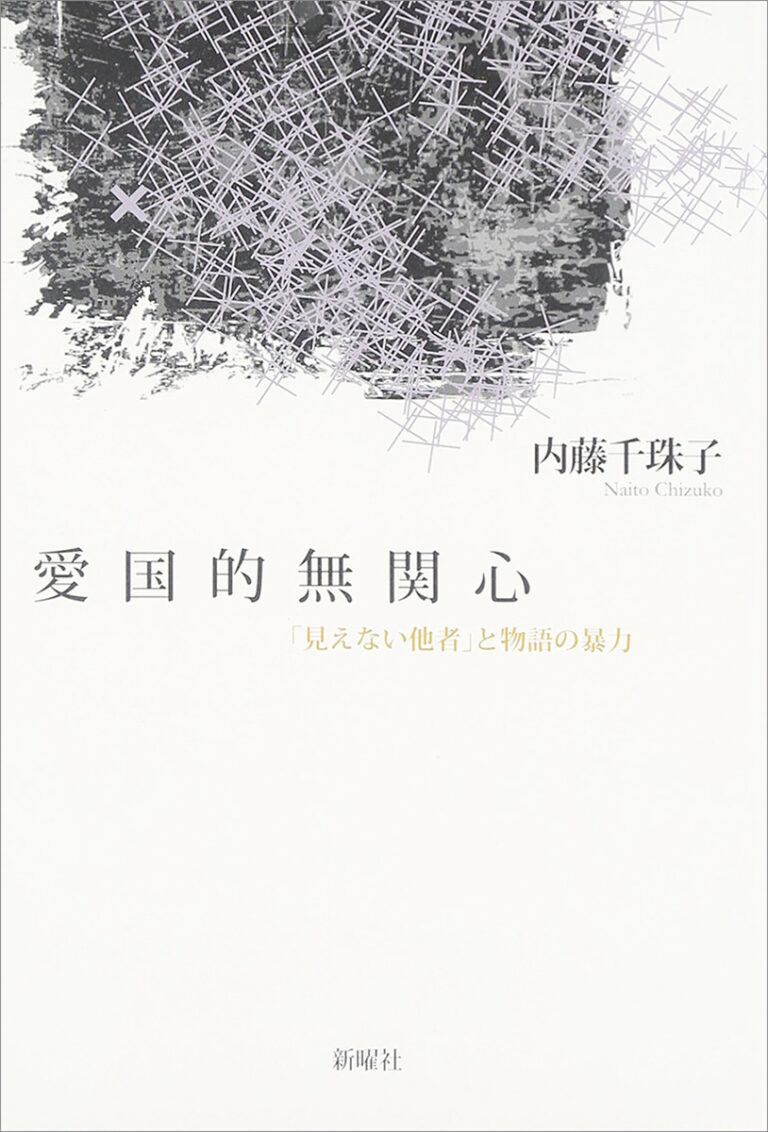[対談]中上健次を「いま」読む意義――中上健次の「思想文学」を論じる
いかにして他者への関心、感受性をたぐりよせることができるのか
内藤 本書『中上健次論』は、思想として読むことと、文学として読むことを同時に実践し実現した、スケールの大きな著作だと思います。中上健次のテクストを読むことと、著者である渡邊さんの思索が共鳴しあい、中上健次を「いま」この現在において読むこと、そして再び読み返すことの意義を伝える一冊となっている。作家・中上健次やそのテクストが入口にあることは間違いないですが、文学を出発点として、何をどのように思考しうるのか、学術的な領域が押し広げられる印象を受けました。現在は、複数の次元で既存の価値観が問い返され、認識をめぐる転換期を迎えている気がしますが、一方ではヘイトや暴力が標準化し、コロナ禍で人と人との関係性や距離感がネガティブに、不安定な方向に変貌しつつもあります。新たな意匠をまとった国家・資本や帝国主義の暴力の様態を、本書は、広範囲に及ぶ学術的知見を踏まえた視座から問い返しており、極めて高い批評性と思考の指針が示されている。まずは、「いま、中上健次を読むこと」について、どのような「現場」を思い描き、どこに向かって執筆したのか、おうかがいしたいです。また、本書のタイトルは「中上健次論」ですが、どのような意志がこめられているのか、あるいは、他のタイトルの付け方もありえたのかどうか、あわせてお聞かせいただけるでしょうか。
渡邊 中上健次は1992年に亡くなっていますから、それからすでに30年の時が流れたことになります。中上について、これまで多くの言葉が紡がれてきましたが、内藤さんの中上論やお仕事は、わたしがこの本を書くにあたって、あるいは、中上だけでなく、文学の言葉について考えたり書いたりするにあたって、つねに重要な参照項のひとつとしてありましたし、いまもあります。どういった点に触発を受けてきたのかについては、今日の対話においても、直接、あるいは間接にも触れられることになると思うのですが、それをひとつだけあげると、文学を通じて、文学を基点において、過去や現在、歴史や現代社会を思考しようとする、クリティカルな構えです。
「いま、中上健次を読む」、その「現場」や言葉の宛先についてですが、まず、わたし自身の「現場」についてお話しすることからはじめるといいかもしれません。「現場」とは、特定の時空を生きること、特定の時間を特定の空間で生きることですが、それは、あるひとつの歴史を生きることにつながっていると思います。それは、固有な経験であると同時に、こうして語ることを通じてある抽象性も帯びていて、言語化されることによって虚構化され普遍化されもする、特殊でありつつ普遍的であるような時空です。政治学者で詩人の李静和さんは、そのような時空を指し、とりわけ、傷を抱えて、語りえない記憶を沈黙のなかから語り出そうとする、その「未発の声」を受け止める場として「現場性」という言葉を「発明」しました。この「現場性」は、本書にとって多くの触発を与えてくれた重要な「構え」のひとつです。
「現場」にもどると、本書は非常に長い時間をかけて書かれた本であるために、ここには書き手である「わたし」にとって複数の「現場」、複数の歴史が重層的に折り重なっていて、それ自体が「現場性」を帯びています。そのひとつは、東日本大震災と原発事故です。2011年3月、わたしは、中国大陸の天津にいて中国の大学で日本語文学を教えながら、博士論文を書いていました。言わば、東北にも東日本にもいない、そもそも日本列島にもいない、つまり、いわゆる「現場」にはいなかったわけですが、しかし、この震災と「原発事故」という出来事が投げかける問いは、この本を書く、その根底に大きな歴史的な問題として横たわっています。震災と「原発事故」のあと、社会科学の領域では戦後の開発主義を再び批判的な検討に付すことがなされ、また、文学研究においても、「原爆文学」や「震災後文学」といった視座から出来事への問いが深められてきました。同時に、開発主義を批判的に思考するために、重要な思想資源となりうるような思想や哲学の言葉を「発掘」する作業も複数的に進められてきたように思います。わたしは、日本語で書かれたもののなかで、そうした思想資源となりうるものはなにかと考えたとき、そのひとつとして、中上健次の言葉を読むことができるのではないか、と思いました。当時、そして、現在も、そうした文脈で中上健次を読む、あるいは、読み直すというような機運はあまり見られなかったのですが、わたしは、いまこそ、中上の言葉を読み直してみたい、と思ったのです。
別の言葉で言えば、開発主義や生産主義、効率主義に抗する思想資源として中上文学を再文脈化することで、多様な価値を潜在させる中上健次の言葉の価値を「再発明」することができるのではないか。そのように思いましたし、それは、安易な現在主義ではなく、わたしたちの「いま、ここ」、その現在地としての「現場」が、なぜ、このようにあるのか、批判的に考えるために必要であり、重要な作業ではないか、と感じました。(再)開発や生産主義は、けして過去のものではなく、二回目の東京五輪を終え、大阪万博が繰り返されようとしている日本社会や現代世界を、いまも強く規定しています。つい先日も岸田首相は、原子力発電所の新規増設を打ち出しました。「原発震災」が起こり、そして、未曾有のパンデミックを経てもなお、それはわたしたちの社会や生活を捕縛している。また原子力発電所で作業する「原発ジプシー」(堀江邦夫)とも呼ばれる被曝労働者のなかには、在日朝鮮人や沖縄奄美の人々とともに、少なくない被差別部落の人々も含まれているとも聞きます。こうした点からも、中上文学を差別と表裏の開発という史脈のなかに位置づけ、読む必要があるように思います。
このようにして、まず、やや大きな歴史的な文脈のなかで、「いま、中上健次を読む」ことを考えた、時代状況と向かいあうなかで発想し構想した大上段の企てではあるのですが、その具体的な作業は、中上の言葉を読む、つまり、中上が遺した言葉、彼の「死後の生」である言葉と対話をすること、つまり、非常にプライベートな、私的な時間の積み重ねです。そうした時間の最終段階で、コロナ禍がおきました。現在もヒトヒト感染で広がることをやめないウイルスは、「わたし」が他なるものたちで構成されていることを端的に示すものです。「わたし」たちは、すでにつねに他なるものに浸食されていて、他なるもので構成されている。コロナ禍は、大きな犠牲を払うことを強いながらも、わたしたちに、自らの内なる他者性、他者に依存し相互浸透しているわたしに気づかせる契機ともなりうる出来事だとも言えますが、しかしながら、現在の社会は他なるものの否認を標準としていますよね。パンデミック下で肯定的に強調される「家族」や〈絆〉は「われわれ」という同質的な共同体であり、ヘイトスピーチに見られるような他者の排除、他者への無関心と表裏の相関性にあります。価値や認識の転換期でありつつも、内藤さんが緻密に解き明かされた「他者への無関心」、他者への不感症を根底にもつ「愛国的無関心」はさまざまなレベルに行き渡り、「亀裂」や「分断」をさらに深めているように見えます。
物理的に生身の他者との接触や対話が難しくなり、そうした状況に拍車をかけているようにも見える状況のなかで、では、いかにして他者への関心、感受性をたぐりよせることができるのか。古典的な方法かもしれませんが、そこに文学を読むこと、文学的な言語を読む意義があるのではないでしょうか。内藤さんは、『「アイドルの国」の性暴力』のあとがきで、コロナ禍で生身の他者との交流が寸断されているなかで、すでに読んだ文学の言葉のなかから、かつて論じたときには聞こえてこなかった声が聞こえてきた、そのようなことをお書きになっていたと思います。文学の言葉は、非常に多義的なので、つねにすでにこぼれ落ちてしまうものがあります。だから、あるときは通り過ぎることが許されるんだけれども、同時に、耳をすますことを求める。だからこそ、何度も何度も読み返すことができるし、読み返すことで他なるものに出会い、さらには出会い直すことができるのかなと思います。それを通じて、読み手である「わたし」の感受性や感性が組み替えられたり、思想や思考のあり方が刷新されたりもする。息苦しい社会をすこしでも居心地のよいものにしたいと願うとき、最終的には、それはひとりひとりの感性の問題、感性の変革にあるわけで、文学的言語にはその個別具体の感性に訴えかけることができるものがあると思います。これは内藤さんのお仕事から教わったことでもあり、またわたし自身も「文学研究者」ですから、そのように信じていますし、『中上健次論』は、まさに、そのようなものとして中上の文学の言葉を捉えて読んだものでもあります。
タイトルについてですが、インスクリプトの丸山さんからの最初の依頼が、人文書として『中上健次論』をまとめてほしいということでした。校了間際に副題をつけるかどうか、ということも話しあったのですが、結局つけないほうがいいということで丸山さんと一致しました。わたしの思考の出発点にあったのは、作家論や作品論ではない、中上健次の「思想文学」を論じるということで、そういう意識でずっと執筆していました。本書は雑草のように多岐にわたり多方向に広がる問題を扱っていますが、それらは中上のテクストにおいて交差し関係づけられながら考察されているので、『中上健次論』でいいのかなと、思っています。
内藤 複数的な現場への想像力を持ちながら、歴史的な出来事を共有された大きな問いとして受け止め、かつ、そこにある具体的な個別性を「わたし」がどのように読み、批評の言葉としてつないでいくのか問い続ける渡邊さんのご姿勢は、本書で実践されている叙述のスタイルに結実していますよね。対話的な姿勢をもった思考の広がりを、改めて実感しました。そうした実践を重ねてきた渡邊さんの思考の「間」に、中上健次の言葉がある。本を手に取って『中上健次論』というタイトルを目にしたとき、渡邊さんの強い覚悟がまっすぐ伝わってくるように感じました。
「(再)開発文学」という方法
内藤 本書ではいくつか重要なキーワードが展開されています。まずは全体を貫く、近代的な開発と現代的な再開発を総合する方法論的な概念「(再)開発」あるいは「(再)開発文学」について、その射程と可能性をおうかがいしたいです。この本のなかでは、第一に、被差別部落をめぐって具体性をもった場所や歴史的展開が考察の対象とされ、国家と資本の暴力を念頭に置いた上で議論が展開されています。その上で、「(再)開発」あるいは「(再)開発文学」という概念はさらに、考察対象としての主題や内包される要素を有機的につなぎあわせ、問いの広がりを誘発する概念となっていますよね。差別・被差別化の力学、植民地主義的な構造や関係様式、軍事主義、ジェンダーをめぐる性差別や性暴力、自然や環境、動物への侵略的介入、クィアな関係性の抑圧、労働する身体の商品化などの主題を、個別の要素としてとらえるのではなく、連続したものとして関係的に考察することができる鍵概念として、現代的な諸問題を構造的、論理的に結び合わせており、示唆的な概念だったと思います。この「(再)開発」という概念を有効なものとして見出していく過程には、渡邊さん御自身のなかで、どのような思考の展開があったのでしょうか。
加えて、この方法論的な用語がもつ思想の「構え」として、現在のなかに歴史的想像力を呼び込もうとする力学を感じ、刺激的でしたし、「再編成」「再現」「再演」「再発明」などの運動性や出来事性の捉え方のなかにも、そうした思考の構えが通底しているように感じました。渡邊さんが自覚的に響かせ合うそれらの運動性は、テクストのなかから拾い出される「模倣」や「擬態」の運動の分析とも関連しているようにみえます。「(再)開発文学」という方法の設定は、虚構の空間を構築しながら問いを投げかけるという文学のもつ虚構性、あるいはフィクションの力と関わっていることにつながるようにも思えるのですが、いかがでしょうか。
渡邊 「戦後」の日本列島は、大規模開発の時代を迎えます。敗戦によって植民地を失い、帝国の領土は縮小され、新たに再編されます。その新たな国土のうえに、敗戦後の復興、経済成長期の国土開発や地域開発、都市部や郊外の再開発、軍事基地やダム、原子力発電所の建設など重層的に書き込みがなされ、それは質の変容を伴いながらも今日まで続いています。戦争や植民地主義と質を違えつつも、地続きな現状にあると思います。では、その(再)開発という出来事や、それを支える生産主義的な価値観に、「戦後」の日本語文学はいかなる対峙をなしえたのか。(再)開発という出来事、そして、それを支える生産主義的価値観に「戦後」文学が対峙する、その具体的な有り様を、中上文学を対象に検討してみることを『中上健次論』では試みました。「(再)開発文学」とは、こうした方法論的な関心から設けた分析のための視座であり、言わば方法としての「(再)開発文学」です。
この「(再)開発」あるいは「(再)開発文学」という視座は、人間による人間の支配とともに、人間による人間ならざるものへの支配を問題化することを可能とします。なぜかというと、(再)開発というのは、まず、もともとあった差別、すでにある差別を「活用」し、旧来の差別を浮上させると同時に、新たな差別をつくりだす、差別を生産する面があるからです。したがって「(再)開発文学」は、人間に対する人間の支配、さまざまな差別、植民地主義や軍事主義、性差別やクィアな関係性に対する抑圧など、多様な支配や暴力を対象化できると同時に、開発は人為の自然に対する侵食や植民であり、ゆえに、人間の人間ならざるものへの支配をも問題の射程に収めることができます。中上を現代的に読み直すためには、この双方を、つまりは人間社会の問題と環境に関わる問題の双方を問題化しうる視座が不可欠で、また、わたしたちをとりまく多種多様な暴力を連関させて批判的に思考しうる視座が必要だとも考えていました。それはけしてあらゆる問題に答えるべきだというような意味ではなくて、それらが「いま・ここ」を生きるわたしにとって切実な問いとしてあったからです。また、再開発をつきつめて考えると、そういった問題に行き当たり、それらを考えなければならない。わたしたちをとりまく様々な暴力や抑圧を考えるということが、つまり、(再)開発を考えるということなのだと思います。今回、一冊にまとめるにあたって、これらの問題に向かいあいつつ書くことは、自分自身に課したひとつのハードルでもあったので、その意図をくみとっていただけたこと、そして、もし、それが一定程度成功しているということなら、うれしく思います。
さて、「(再)開発」は、近代的な開発と現代的な再開発の両方を含意する概念ですので、(再)は、一義的には、現代的な再開発に由来するものです。しかし、内藤さんがおっしゃるように、(再)は、再び、re、繰り返しという意味で、現在を過去によって構成されたもの、過去の亡霊的な再現として現在を捉える、現在を過去と関連づけ歴史化する運動性としても捉えることができるように思います。また同時に、この(再)は、表象や虚構化という意味も少なからず帯びていると思います。言語によって構築され、表象によって歪められ、虚構化される。言わば、フィクションは、対象を模倣し、擬態するわけですが、しかし、その行為が運動性を持つがゆえに、生命力や偶発性に満ちたパフォーマンスであるがために、正しく擬態できない、そこにアクシデントが生じ、つねにズレや逸脱、雑音が生じ、不適切な擬態になってしまうわけです。フィクション、虚構の魅力のひとつは、この偶発性にさらされ、変わってしまうこと、変えられるということそのものであり、さらに言えば、変わることも変えることも可能だと感じさせることではないでしょうか。フィクションを通じて、読み手であるわたしたちが得るのは、この「変えることができる」という感触、その可変性の可能性ではないかと思います。いま、わたしは、小説や物語などの虚構をさして、フィクションという言葉を使っています。しかしながら、フィクションという語がさすのは、虚構だけではありません。現実の政治機構、法や制度もまた、人為によってつくられた、
構築されたという意味でのフィクションとしての制度、擬制であり仮構です。しかしながら、多くの場合、小説や物語を虚構として、あくまで作りものとして扱うのに対し、擬制や仮構としての制度は現実として変更不可能な所与のものであるかのように思い込まされています。しかし、はたしてそうでしょうか。フィクションとしての虚構が変えられるのなら、同じフィクションである「現実」の制度もまた、たとえそれがどんなに大がかりなことになったとしても、同様に変えられる可能性に開かれているのではないでしょうか。虚構というフィクションは、「現実」の制度というフィクションもまた変わりうること、すなわち、わたしたちの社会や世界を変えることができるかもしれない、そのことに気づかせてくれるように思います。フィクションとはまた、この変わりえることの希望を手渡す言葉の機構と言えるのかもしれません。
内藤 各論に言及すると収拾がつかなくなるので自制しますが、いまのお話と関連することで一点だけ触れると、第一章で非常に魅力的に展開されていたのが、「一番はじめの出来事」の分析でした。フィクションに含まれる模倣や擬態の運動がきわめて「不適切」に行われることによって、何かを変型させる可能性が生まれる。その「不適切」さは、そもそもフィクションであり作り物ということが前提とされている小説のなかだからこそ、可視化の契機をもち、現実世界にも可変性は生じうるという手応えが派生する。本書の叙述からは、渡邊さんのおっしゃる「変えることができる」という感触が、確かに伝わってくるように思いました。
「仮設」の「路地」のビジョン
内藤 続いておうかがいしたいのは、「仮設」についてです。複数性や両義性、境界性をもち、力が潜在する「仮設」の空間として「路地」を読解し、考察することによって、未完の時間、過程の時間に現象する、身体性をともなった出来事や関係を可視化するという論理を興味深く拝読しました。「仮設」の路地における「(再)開発」の動力としての交換や交通の運動を見ていったとき、透明に見えがちな「媒介」行為に含まれる抑圧性、権力性の問題が浮上してきます。五章では、土地から疎外される被差別部落の人たちが、資本を得る手段として土建業という「媒介業」につき、「(再)開発」に関わっていくけれども、そのとき、個や複数は主体化し、かつ受動化した位置にあるということが析出されています。七章では、二つのシステムをまたぐ「媒介者」の知が、等価交換の装いをした不等価交換を行なったり、境界線を自由に画定できる権力をもったりすることなどが批評的に考察されていました。媒介者のもつ抵抗と反動の両義性や、権力を援助する可能性と権力を告発・批判する可能性を同時に帯びるという両義性は、潜在する力として、「仮設」の空間のなかでは未完の時間、過程の時間に宿っていることが読み取られていきます。七章では、その「媒介者」の場所に、まさにわたしたち読者がいるのだという位置づけがなされていて、緻密に構成された論理に基づく、批評的な強度を感じました。八章では、『千年の愉楽』の考察で、オリュウノオバの語りについての分析がありますよね。オリュウノオバの語りがもつ「媒介」の運動を重ねて検証していくと、本書に示された「仮設」と「路地のビジョン」について展開があるように感じました。
渡邊 「未完」の魅力、その可能性について、内藤さんはかつて漱石の『明暗』に触れつつお書きになっていて、以後もずっと追究されていますよね。「仮設」は、完結していない、ゆえに未決の両義的な過程の状態性です。特定の意図や目的に回収される(再)開発や、それを支える生産主義や効率主義に対して、「仮設」の潜在的な力、未決である過程の、その権能において、歴史は複数の方向に開かれています。本書では、このような点から、「仮設」の路地に、(再)開発への抵抗性を読み、さらに脱国家的で脱資本的な社会を志向する「路地」のビジョンを見出しました。「仮設」の潜在的な力、権能において、歴史と同じく、出来事の意味もまた、一義的な意味や物語に回収されない、多方向性を帯び、多義性に満ちています。そうであるからこそ、出来事や関係性が可視化されうると言えると思います。というのも、この世界はそれほどに単純でもなく、むしろ複雑で入り組んでいて、そこに起こる出来事もまた単純明快ではない、白黒はっきりした二元論で割り切ることはできない場合も少なくなく、暴力や差別、支配の問題についてもそのような部分があるように思います。たとえば、
本書では、重層差別や複合差別を問題化する小説として『熊野集』の短篇を読み解きましたが、被害者が加害者でもあったり、ある局面での被害者が別の局面では加害者であったり、不特定な加害者によって被害者が生じたりするような重層的な差別の問題を、中上は、情動にも関与する多義的な文学的言語ですくいとっています。歴史や出来事を生きる人々は、その身体をすでにつねに法や制度に絡め取られていて、とりわけグローバル化による脱領域的な移動や相互浸透は、その絡まり合いをより複雑なものにしているように思います。本書では、「公共」という概念も重視していますが、それもまた、絡め取られていることへの対峙という問題意識の延長線上でなされた思想的選択でもあります。
このように、それ自体、両義的であり多義的でもある複雑な世界、複雑な出来事を複雑なままに描きとるには、ある特定の意図や目的で論理を運び、特定の意味づけをし、特定の因果関係のみで説明するのでは十分ではないと思います。多方向に開かれた、未決の潜在的な力においてこそ、その複雑な出来事を、その入り組んだ、多義性を帯びた関係性を、掬い/救いとることが可能なのだと思います。八章で扱った、因果関係を破綻させる『千年の愉楽』のオリュウノオバの媒介的な語りがまさにそうであるように、路地のビジョンとは、出来事や関係性を可視化する開かれた物語であり、未決の開かれた言語とも言えるかもしれません。これは、内藤さんが『「アイドルの国」の性暴力』で示された、ひとつの声や論理が支配するのではなく、互いに他を力で排することをせず、異なる価値が並び立つ地平を開く、「共鳴のフレーム」と通じ合う部分があるのではないか、と思います。
内藤 おっしゃる通り、多義性を排除しない思想のフレームをどのように生みだしていけるのかが重要ですし、対話的な議論を共有していきたいですよね。いまお話にあった「路地の公共性」ですが、「群れ」の思想との接続点からお聞きします。渡邊さんが示した、複数的、多義的で、部分が全体の一部ではなく、全体が部分の総和ではないという「群れ」の思想、中上健次のテクストにおいて再発明された「集団と個」を見出していく読解の手続きは、「わたし」と「わたしたち」の関係をどう捉えるのかという論点ともつながり、現代の諸問題を考える上での深い洞察を与えてくれます。鬼の女たち、そして路地の女たちの声、中本の一統のアニたちなど、単独でははかなくて可視化することが困難な身体や声を、「群れ」や「雑草」が形象化することの意義は、「路地の公共性」「非所有の所有」と交点をもっていて、このことは、記憶の抑圧や集団的な忘却という問題、あるいはトラウマ的な記憶の問題と接続させて考える可能性として手渡されているように思いました。渡邊さんの組み立てた論理に触発されるように考えていくと、抑圧されてしまうマイノリティの側の記憶や、歴史的な記憶、沈黙を強いられる声、衝撃的な暴力を受けた者の声ならざる声に寄り添い、隣り合う場所を、「群れ」の思想は実現しうるのではないでしょうか。忘却されることが当然視されてしまうような記憶を、誰のものでもあって誰のものでもない、「非所有の所有」である記憶へと組み換える批評性を本書は示していると思います。
渡邊 〈路地の公共性〉を、〈記憶の公共性〉、〈言葉の公共性〉として、群れにおいて実現できるのではないか、ということですよね。とても魅力的なアイディアで、触発されます。「非所有の所有」とはもともとは森崎和江の概念ならざる概念で、闘いとエロス、運動とジェンダーをめぐる問いのなかで深められた思想です。資本制と家父長制の下で二重の困難な位置にある「女」たちが求める支配なき集団性や水平的な関係性、運動性は、いかに可能なのか。最近、復刊された森崎の『非所有の所有』の解説のなかで、大畑凛さんが論じられているように、森崎は、その可能性を、「所有してない/されていない」非所有の状態性を私有でも共有でもなく所有するという流動的な契機のうちに見出しました。つまり、家父長制的な運動や組織に疎外された「女」たちによる、それとは異なる運動性や集団性への希求において、森崎の「非所有の所有」の思想は紡ぎだされていると言えます。
対して、本書では、その「女たち」を、斜め線が引かれた「女」たちという方向性において広げ、様々なマイナーな存在たちを含意させています。また本書では、資本主義社会と近代国家体制を根底において支えるという意味で、私的所有を批判的に対象化し、誰のものでもないがゆえに誰のものでもあるという地平を含意させ、「非所有の所有」という言葉を主に使っています。立岩真也さんが論じるように、所有するということは、すなわち処分可能であるということです。所有は、とりわけ新自由主義的な社会においては、その対象を処分できる可能性、あるいは、最終的に処分してもよい、という感性と結びついています。資本主義体制下において、私的所有権は、土地をはじめとするさまざまな商品を処分可能性にさらすと同時に、労働力化され商品化された身体にも、処分可能性を及ぼすに至っているように思います。つまり、所有してはならないものまで所有してしまっているのではないかという問題です。当事者の声や歴史的な記憶もまた、他者が勝手に所有できないもの、所有してはならないもののひとつです。〈路地の公共性〉の言語レベルでの実践として、単一の意味の所有とは異なり、多義的で重層的な所有ならざる所有、「非所有の所有」にある言語論を、本書の第五章では示したのですが、それは、もう少し広く、〈記憶の公共性〉や〈言葉の公共性〉へ展開可能なのだと思います。その場合、本書の「非所有の所有」とは、自分のものではない記憶や声、声ならざる声に寄り添い、隣り合うメチエとしても見えてきます。先ほど述べたように、「非所有の所有」という概念を、誰のものでもないがゆえに誰のものでもあるという含意でわたし自身は使用していますが、その経験、その記憶は、他者である「わたし」は所有できないし、所有してはならない。それは、わたしのものではない。けれど、だがしかし、その経験、その記憶は、わたしのものであったかもしれない、その経験した誰かは、自分であったかもしれない、そういった処分でも所有でもないかたちで「わたし」が「わたしたち」として連なりうる感性や地平を「非所有の所有」は聞くことができるように思います。逆に言えば、潜在的な権能に満ちた「群れ」が国民や市民の集団として、性差別や民族差別など集団的に憎悪や敵意を行使し、暴力性を発動させる。その瞬間、「群れ」は、「非所有の所有」を手放している、「非所有の所有」を放棄してしまっているとも言えるかもしれません。
内藤 なるほど、「群れ」に潜在する両義性ということですよね。誰のものでもないかもしれないけれども、誰のものでもあって、それを「わたしのものであったかもしれない」と考えていく認識のあり方を通して、現在の二元化された暴力、他者を敵に見立ててしまう発想を組み替えるためには、繊細な注意深さを持ち続けることが重要だと、お話をうかがいながら改めて感じました。
「現場性」の感触
内藤 最後に、「起源」とは異なる「はじまり」についておうかがいします。単一の起源を想定してしまうのとは異なる、複数性を帯びた「はじまり」について論じていらっしゃいますが、そうした視座から、読者としてこの『中上健次論』をそのような「はじまり」と見立て、さまざまに考えさせられました。本書のなかでは、「なぜ?」という、当事者にとってはつねに切実な、終わりなき問い、終わりなき悲嘆、答えのない問いについても論じていますが、それを絶望とは違うかたちで広げていく、文学の言語がもちうる方向が示されているように思います。起源を想像することは、因果関係による擬装された「完結」を呼び込んでしまうのかもしれません。どんなに繊細に考えようとしても、因果関係が呼び込んでしまう「罠」がある。たとえば「海神」の分析では、大逆事件が「おわりのはじまり」として呼び込まれたときの暴力性が議論されていますが、「完結」という因果関係は実のところ、意想外の権力性を内包しているわけですよね。
この本のなかには、「自らを裏切る可能性を抱えた言葉の表現」、「表現できないものへ手を伸ばし届かせようとする言葉の不屈の表現」というフレーズがあります。フィクションであるからこそ生じうる、当事者には語り得ない言葉を言語化する可能性は、「代弁」とはすこし違ったかたちで、読んだ側を、当事者が立つ終わりなき問いの時間、問いや悲嘆が切実に響き渡り続ける過程の時間に引き入れる力をもつのではないか、そのような次元を創造しうるのではないかという、具体的な手触り、手応えが伝わってきました。当事者性については、議論の積み重ねや新しい視座の構築もありますが、「はじまり」がもつ思想的な可能性と関わらせて、お考えや見通しを聞かせてください。
渡邊 8月30日に、わたしは京都地方裁判所にでかけました。友人とともに京都、宇治のウトロ放火事件の判決を傍聴するためで、けっきょく法廷には入れなかったのですが、その後の記者会見や集会に参加し、お話をお聞きしました。ウトロ地区は、いわゆる在日朝鮮人、韓国人の集住地区で、いわゆる「不法占拠」地域です。この事件は異例とも言えるほどメディアでも大きくとりあげられましたが、はたして裁判でヘイトクライムとして位置づけられるのかどうかが焦点となっていました。このいわゆる火つけ、放火事件との関わりで想起され、考えたことのひとつが、『地の果て 至上の時』のラストで、本書の第九章はそれを論じています。竹原秋幸と思しき人物が、路地跡の空き地、その雑草の草むらに火を放つ場面です。この場面は、秋幸の実父、浜村龍造を反復する、それを繰り返す行為、まさにre(再)としての文脈をもつものです。龍造は、戦後、路地的な場所に火つけをする。そうして住民をおいだしたうえで、その地を売り払って、資本を得ていく。地域の有力者である佐倉の片棒を担ぎ、その現場で実行犯を担った人物です。ここには、戦後、開発によってなりあがっていく、上昇気流にのろうとする、そうした経済的上昇への欲望があります。先日インタビューをお聞きしたのですが、紀和鏡さん(中上かすみさん)によると、中上は、生前、浜村龍造は田中角栄のような人物だと言っていたそうです。そして、同時に、龍造の放火には、路地に入り込もうとしながら拒まれた龍造の私的な、個人的な路地への憎悪、報復的であり差別的でもある情動が背景にある。そのようなものとして、小説のなかでは描かれています。
これに対して、『地の果て』の最後、秋幸がつける火は、これとは違う部分がある、と本書では論じました。21世紀の現代において、つけ火や放火は、たとえばウトロの火がそうであったように、龍造の火が携えていた憎悪と差別を排外的に先鋭化させて、社会にくすぶっているように見えます。弁護団のおひとり(上瀧浩子弁護士)も強調なさっていましたが、差別や憎悪の表現や行為は、どこまでやっていいのか、これくらいならやっても許されるだろう、そういったメッセージを事件それ自体で表し、試すような部分がある。『地の果て』のラストのつけ火は、現代の差別を照らし出す鏡のようにわたしには見えます。もちろん、そこには、被差別部落と在日朝鮮人という重大な差異もあるわけですが、その差異を含めて、中上の文学を読むことを通じて、差別の歴史性を問い、その暴力に批判的に向かいあうこともできるように思います。
現代的な差別という点では、こうしたヘイトクライムとともに、ネット上での差別があげられます。たとえば、ネット上で被差別部落の場所を可視化するといった新しいかたちの差別で、ある人が被差別部落の場所を、本人の意思と関係なくネット上で拡散するという問題が起こっています。社会学者の友人のフィールドワークに同行させてもらった際に聞いた話ですが、日常的な差別は無くなった、少なくなったという声を耳にしました。ネットリテラシーには濃淡があり、人によっては、ネット上で差別されていても気づかない、知らないうちに差別されているようなケースがあります。その場合、本人の意思とは関係なく、しかも知らないうちにアウティングされてしまうことになります。
いまお話ししてきた内容は、当事者の証言をどのように聞き、どのように語るのか、その具体的なコンテクストです。「代弁」の暴力とともに、こうした暴力もあるということなのですが、そのことで、言葉を繰り出す回路のあり方がさらに問われることになっているように思います。
中上健次は、和歌山県新宮市の被差別部落を路地として表象しています。路地は一方で、ある固有の土地や経験と結びついていますが、一方で、「自らを裏切る言葉の可能性」によってつねに抽象化され普遍化されています。固有でありつつ抽象的であり、特殊でありながら普遍的でもある「現場性」の言葉で、不可視化された暴露の暴力とは異なる回路を宿し、暴力性とは異なる感触で、当事者の経験や記憶を運んでいるようにも思います。さらには、そこに、「代弁」するのとは違うかたちで、「表現できないものへ手を伸ばし届かせようとする言葉の不屈の表現」によって、当事者には語りえないなにかを語る言語が兆す可能性があり、そこに読み手と複雑な関係性を結び得る、未完の物語、過程の言葉が兆すように思います。そのとき、未完であること、未決であること、「仮設」であることがやはり重要なのだと思います。完結して区切られているということは、遮断されているということです。その遮断がされておらず未完であるということは、読み手が関わる糸口があるということなのだと思います。また、未完である、開かれている、多義的で複数的であるからこそ、排除することなく、「わたしのこと」として読み手が考えられる余地や契機があるのだと思います。その意味では「終わりのなさ」とは、「関わりが途切れない」ということだとも言えると思います。
すでに述べたように、この対談のなかで使用してきた「現場性」という言葉は、李静和さんの『つぶやきの政治思想』からの引用ですが、「慰安婦」とされてきた女性たち、ハルモニたちの沈黙に寄り添い、語り得ない言葉に、どのように手をのばすことができるのか、そのための言葉を模索するなかで生み出された言葉です。「分からないこと。分かってはならないこと。消費するのではなく受容しなければならないこと。それは語る私に、聞く我々に、居心地悪さを残す。外部からはどう解釈してもいい。だが、いったん枠に入った瞬間からは、解釈することを拒否しなければならない。/それが生きる場だから」。元「慰安婦」とされたハルモニたちの「生きる場」によりそうための構えや言葉を探し求めて紡ぎだされる、この具体性と抽象性をともない、単独的でありかつ普遍的でもある言葉、未完で未決の過程の、「仮設」の言葉、その「現場性」の感触に、現在的な差別の暴力性を批判的に対象化し、それとは別様の言葉の回路を開くことができるような気がしています。(了)
2022.09.15
内藤千珠子
近現代日本語文学、ジェンダー研究。大妻女子大学文学部教授。著書に『「アイドルの国」の性暴力』、『愛国的無関心─「見えない他者」と物語の暴力』、『帝国と暗殺―ジェンダーからみる近代日本のメディア編成』(以上、新曜社)、『小説の恋愛感触』(みすず書房)ほか。
渡邊英理
日本語文学、批評。大阪大学大学院人文学研究科教授。著書に『中上健次論』(インスクリプト)、『『クリティカルワード 文学理論』(三原芳秋、鵜戸聡との編著。フィルムアート社)、『〈戦後文学〉の現在形』(共著。平凡社)など。