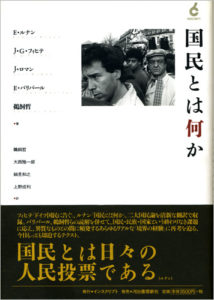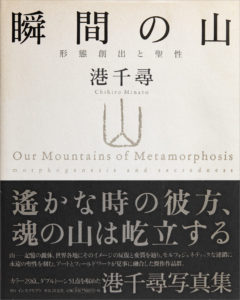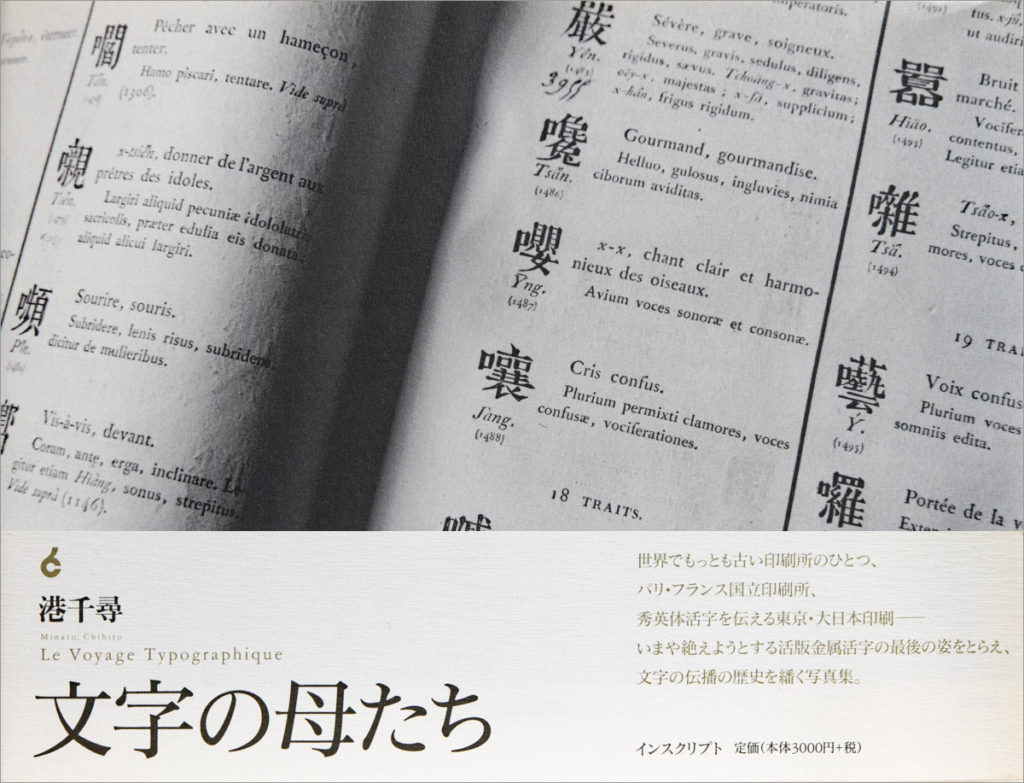わたしがヴィクトル・セルジュの名を知ったきっかけは、トロツキーとの関連ではない。20世紀前半の旅する芸術家を扱った『熱帯美術館』(共著・リブロポート)のなかで、パリで生まれたシュルレアリスムが海を渡って拡散してゆく様子を書いたことで、その名を知ったのだった。それはアンドレ・ブルトンが所蔵していた資料にある。
メキシコに亡命していたトロツキーやフリーダ・カーロに出会ったブルトンは、パリに戻った後、ヴィシー政権下のフランスでマルセイユに避難していた。フランスへの海の玄関口マルセイユには、新大陸へと避難しようとしていた人々が集まり、パリからも多くのアーティストや作家が周辺に滞在していた。その中にはキューバを代表する画家ウィフレード・ラムやクロード・レヴィ=ストロースもいた。最終的にブルトンはこれらの人々と同じ船に乗ることになるのだが、そこにはドイツ人写真家のジェルメーヌ・クルルも乗船していた。マルセイユでヴァルター・ベンヤミンのポートレートを撮影したことでも知られるクルルがいたこともあって、ポール・ルメール船長号という名の「難民船」の様子は、すくなくともシュルレアリスム関係の資料としては比較的知られている。その旅の最中に、甲板などで撮影された写真のなかに、ヴィクトル・セルジュも写っていたのである。
船が出るまでの間、ブルトンがバンジャマン・ペレ、画家のレメディオス・バロといった友人たちと滞在していたのは、マルセイユ近郊にあったシャトーだった。「ヴィラ・エア=ベル」と名づけられた館には十分な広さがあったようで、知り合いの知り合いをたどるようにして、さまざまな人が到着していた。新大陸への査証を待つ人々のアジールとなったこの館で、セルジュと息子のヴラディ、妻のロレット・セジュルネも一時生活を共にしていた。
このヴィラで撮影された写真は、戦後ブルトンが監修した雑誌『シュルレアリスム・メーム』(Le Surréalisme Même)の第2号に収録されている。ブルトンと談笑するペレとバロの隣でうつむき加減でタバコを加えている男がいる。同じ男は船で撮影された集合写真でもいちばん端で同じようにうつむいており、カメラには興味を示していない様子である。集合写真はたいていカメラに顔を向けて微笑んでいるものだが、たまにこういう態度の人物がいることがある。後になって、要注意人物だとわかることもある。
いつ画面の外に出てしまってもおかしくない、キャプションが無ければ忘れられてしまうような立ち位置だが、表情が見えないだけ気になるのだ。本名ヴィクトル・ルヴォヴィッチ・キバルチッチとして1890年ブリュッセルに生まれ、28歳でボルシェビキ革命に参加した後、フランス、スペイン、オーストリアを渡り歩きながら革命家として生きたヴィクトル・セルジュ。20年のあいだに四度の亡命、七回目の逃亡生活に入ろうとする人の姿であある。結果その写真は、ヨーロッパ最後の地でのひとコマになったのだった。
ヴィラにはそれなりのライブラリーがあり、週末ともなればパリの知識人や芸術家たちも訪れて、一種サロンのような場にもなっていたという。訪問客のなかにはマックス・エルンストやアンドレ・マルローもいた。ブルトンは滞在中『ファタ・モルガナ』を書いており、いっぽうセルジュは『トゥラーエフ事件』の執筆を開始していた。滞在客らとともにふたりはライブラリーなどで、書いたものをそれぞれ朗読することもあったという。夜の時代のなかで、亡命を覚悟しなければならないような毎日のなかで、ふたりの声はどう響いたのだろうか。セルジュは英国的な紳士を思わせる端正さと柔らかな声が印象的だったという。



ヴィクトル・セルジュは常に現在形、ではないだろうか。時代の強大な力と正面から向き合い、権力の臓腑を見つめつづけた者にしか書けない言葉だからこそ、時代を超えて新しい。ロシア革命に参加したセルジュはモスクワで、帝政ロシアの秘密警察の内部資料を調査する仕事についている。ロシア帝国ではアレクサンドル二世の暗殺の後、内務省の警察部警備局、通称オフラーナと呼ばれる秘密警察が設置されたたが、セルジュはその活動の全貌を、関わった人物の個人的経歴も含めて、精査することになった(ちなみにセルジュの両親はナロードニキ支持者で、アレクサンドル二世暗殺事件をきっかけに、ベルギーに亡命していた)。
セルジュ自身はこのときの仕事を、「秘密警察研究」とも言うべきかたちでまとめた著作として、1926年フランスで出版している。当時すでにソ連はスターリン支配下にあり、同年モスクワに戻りトロツキーの一派に加わったセルジュは、出版の一年後には共産党から除名され、逮捕されることになる。同書でセルジュはスパイ活動、挑発、尋問など秘密警察の手口を具体的に説明しながら、これに対抗するには何が有効かを「革命家へのアドバイス」として付記している。警察権力の分析を通して得た知識から、対抗のための戦略を引き出したというわけである。
オフラーナのメンバーの一部はレーニンによって設立されたソ連の秘密警察チェーカーに吸収され、悪名高いチェーカーの遺産はスターリンの死後KGBへと引き継がれて、ソ連崩壊後はさらに……という歴史のなかで、セルジュの著作は完全に忘れ去られた……かに見えた。
ところがおよそ80年後、思わぬところで、復活するのである。『国家による抑圧についてすべてのラディカルが知るべきこと』なるタイトルで英語版が登場したのは2005年。これはアメリカ同時多発テロ事件の後、たった45日間で成立した通称アメリカ愛国者法のもとでテロリズムの定義が拡大され、民間人を対象にした諜報活動や拘束や尋問が増加するなかで、日常化した人権侵害を背景に出版されたものだった。
1926年版のオリジナルから訳出され、アメリカの人権派弁護士の序文が付された本のサブタイトルは「アクティビストのための手引書」である。150ページに満たないガイドブックを手にしたアクティビストにとって、著者の名もふくめそこに出てくるロシア語の人名は初耳だったかもしれないが、それを除けば内容は十分に「いま」を映し出していた。スノーデン事件が暴露した21世紀アメリカと、セルジュが記録した19世紀ロシアとでは、情報技術という点では比較のしようがないかもしれないが、少なくとも抑圧の技法のうえで差はない。恐怖心を煽る政治が存在する限り、それはなくならない。たとえば、同書がいまの香港で読まれていたとしても、なんの不思議もないとわたしは思う。
ヴィクトル・セルジュにはコヨアカンのトロツキー記念館のような立派な設備はない。度重なる逮捕と投獄と亡命のあいだに、あらゆる持ち物を取り上げられ失ってしまった人を偲ぶことのできる物は、ほとんど何も残っていない。しかしその思想は現在形で生き続けている。目には見えない熾火のようなものだろう。ソンタグの文章のタイトルにある「消し尽くされぬ」という言葉は、「消火不能の」という意味にも取れる。放水車やペッパースプレーをどれほど集めようが、消火することのできない火が、まだこうして燃え続けている。

- 「消し尽くされぬもの」『同じ時のなかで』スーザン・ソンタグ/木幡和枝訳、NTT出版、2009
港千尋(Chihiro Minato)
写真家、映像人類学。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2007年、ヴェネチア・ビエンナーレ日本館コミッショナー、2012年台北ビエンナーレの協同キュレーションを行う。2014年、あいちトリエンナーレ2016芸術監督。
主な著書・写真集に、『群衆論─20世紀ピクチャーセオリー』(リブロポート、1991╱ちくま学芸文庫、2002)、『考える皮膚』(青土社、1993)、『注視者の日記』(みすず書房、1995)、『記憶─「創造」と「想起」の力』(講談社、1996、サントリー学芸賞)、『映像論─〈光の世紀〉から〈記憶の世紀〉へ』(日本放送出版協会、1998)、『予兆としての写真─映像原論』(岩波書店、2000)『瞬間の山─形態創出と聖性』(写真集、インスクリプト、2001)、『洞窟へ─心とイメージのアルケオロジー』(せりか書房、2001)、『文字の母たち』(写真集、インスクリプト、2007)、『芸術回帰論─イメージは世界をつなぐ』(平凡社新書、2012)、『革命のつくり方』(インスクリプト、2014)、『風景論』(中央公論新社、2019)他多数。